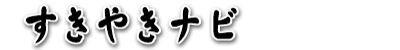肉―4

では次は“牛肉”を少し離れて、“セロトニン”と“トリプトファン”という脳内物質についてお話しましょう。
私たちの脳には、“神経細胞”とそれから伸びる“神経線維”とがびっしり詰まっています。
そして神経線維と神経線維との間には隙間があるのですがそれぞれの神経線維の先に受容体という突起状のものがいくつも付いていて神経伝達物質である“セロトニン”がその隙間で作用して受容体から受容体へと刺激を伝達してくれています。
うつ病の患者の脳内にある“セロトニン”の量は、通常よりも少ないということが発見されてからはうつ病や不眠の薬として“セロトニン”の前段階の物質である“トリプトファン”というアミノ酸が使われるようになりました。
最近では偏った食生活によって内臓脂肪が増え、メタボリックシンドロームを引き起こしている人が多いことから、「肉を控えて魚や野菜中心の食事にしよう」ということがよく言われていますが、“良質”の肉は“脳内物質”の原料として欠くことができないもので、私たちの感情やひいては人生観や性格までもが“脳内物質”の影響を受けているのです。
たとえば私たちは何かがきっかけとなって自信をなくしたり、自己嫌悪に陥ったりして精神的に不安定になると、周囲の環境や自分の考え方に原因があると思いがちですが、実際には脳内物質の不足が大きな原因となって“物事を悲観的にみる傾向”が強くなっていることが多いのだそうです。
そう言われれば、落ち込んだ時 “すきやき”や“しゃぶしゃぶ”、“焼き肉”などをお腹いっぱい食べたら元気がでてきて、目の前に立ちはだかっていた問題が小さくなってきたように感じることってよくありますよね。
また、脳は危険を及ぼすようなものを近づけないために血液中の物質をとりこむのにもとても慎重で、血液と脳との間にあって防波堤の役割を果たしている“血液・脳関門”という箇所を通り抜けるために“トリプトファン”は“担体”と呼ばれるものと結合しなくてはなりません。
そして“担体”は“トリプトファン”だけでなく他のアミノ酸とも結合したり肝臓で分解されたりするために、脳にできるだけ多くの“トリプトファン”を送り込もうと思えば、食物などから多めに摂取する必要があります。
“トリプトファン”は必須アミノ酸の1つで、体内で作ることができないために、食物から摂取しなければなりませんが、動物性たんぱく質に多く含まれることから“肉”も私たちの食生活には欠かせない食材だと言えます。
- 次のページへ:肉―1
- 前のページへ:糸こんにゃく・焼豆腐
スポンサー広告
ネットショップ広告
すきやきナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 河久大阪駅前第三ビル店 大阪府大阪市北区梅田1丁目1−3 電話06-6346-0770
今日のお勧め記事 ⇒ 白ねぎ・春菊
普通のねぎに比べるとやや高価ですが、“白ねぎ”はすきやき料理には欠かせないもので、ぐつぐつと煮て柔らかくなったのは甘くておいしいですよね。 茎の白い“白ねぎ”は別名“根深ねぎ”とも言われ他のねぎとは一線を隔しているように見えますが、実は同じもので、育て方の違いで白い部分が太くて長いものになるようです。 ねぎ農家の人によると、そのコツはまず株同士の距離を短くして脇目が生えるのを抑えながら、表面に出てくる白い茎を絶えず土で隠すという根気のいる作業を繰り返すことで、この作業を怠る
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。